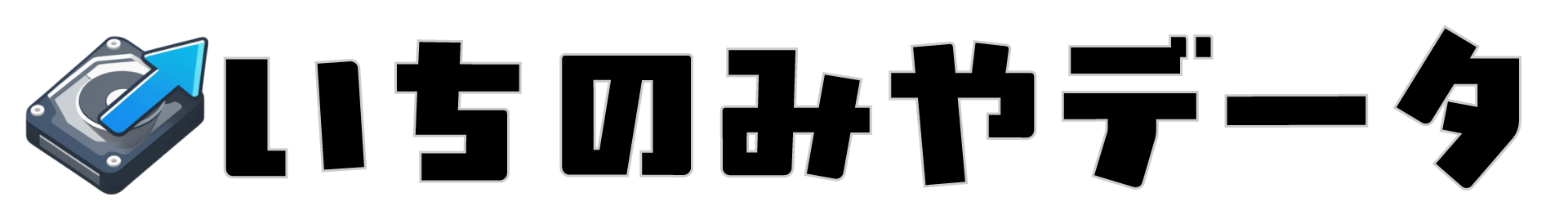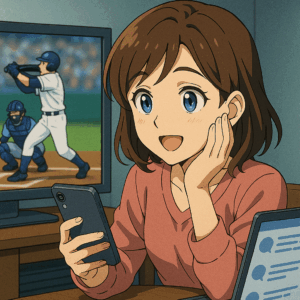アサヒを襲ったランサムウェア集団“麒麟”(Qilin)とは? 世界中で被害多発、カルテル結成でさらに勢力拡大も
アサヒグループHDを狙ったサイバー攻撃で、ランサムウェア集団「Qilin(麒麟)」が犯行を主張。国内工場は順次再開したものの、業務や開示に影響が及びました。QilinはRaaS(サービスとしてのランサムウェア)を掲げ、二重恐喝やLinux/ESXi対応の亜種を用いる高度な集団として警戒されています。
データ復旧技術者の視点:暗号化“だけ”では終わらない
二重恐喝が標準化
Qilinは、データの暗号化と窃取データの暴露脅迫を組み合わせる二重恐喝で圧力を高めます。復号で業務は戻せても、流出の有無・範囲は別問題。初動で外部接続遮断→ログとバックアップの保全→範囲同定を並行させ、将来の説明責任に備えることが肝要です。
Linux/ESXiも射程に
Qilin(別名Agenda)はWindowsに加え、Linux/VMware ESXiを狙う変種が確認されています。仮想基盤の管理ネットワークは分離し、管理系認証はパスキー+短命トークンなど“盗まれにくい要素”へ移行を。
プログラミング講師の視点:RaaSの“ビジネス合理性”に学ぶ
役割分担で攻撃効率が最大化
QilinはRaaSモデルで、コア開発・インフラ提供と実行犯(アフィリエイト)を分業。侵入はフィッシング、脆弱性悪用、盗難資格情報など複合手口が主流です。開発現場では秘密情報のハードコード禁止/SBOM整備/脆弱性SLAを“開発プロセス”に埋め込み、攻撃の“費用対効果”を下げる設計が必要です。
Webエンジニアの視点:連合化報道と“検知で終わらせない”運用
“連合”の報道と見解の相違
2025年10月、LockBit・DragonForce・Qilinの連合(カルテル)報道が相次ぎました。一方で、発表源や実態に対する懐疑も出ています。いずれにせよ、攻撃側の戦術・インフラ共有が進む前提で防御面の連携を高めるのが現実解です。
検知→隔離→復旧の自動化
監視は“気づく”だけでは不十分。EDR/MDRのアラートをネットワーク隔離・特権停止・復旧プレイブックに直結し、人的判断の遅延を最小化します。特に管理系(VPN/仮想基盤/IDaaS)はゼロトラスト+最小権限+短命認証で「横移動」を封じます。
企業が今すぐ取るべき実践チェックリスト
- 重要資産の分離:仮想基盤・バックアップは管理網と本番網を物理/論理で分離
- 認証強化:全社パスキー化、特権操作は端末紐付け+二経路承認
- バックアップ:3-2-1-1-0原則(オフサイト+イミュータブル)と四半期ごとの実地リストア訓練
- 運用自動化:EDR検知→自動隔離→ロールバックのプレイブック整備
- 委託先統制:脆弱性SLA・監査ログ仕様・再委託ポリシーを契約で明文化
まとめ
QilinはRaaSの合理性と二重恐喝、そしてマルチOS対応で“実害”を増幅する集団です。連合化の真偽を巡る議論はありつつも、防御側は分離・最小権限・自動隔離・イミュータブル復旧を標準装備に。今日できる小さな設定変更が、明日の被害を確実に減らします。