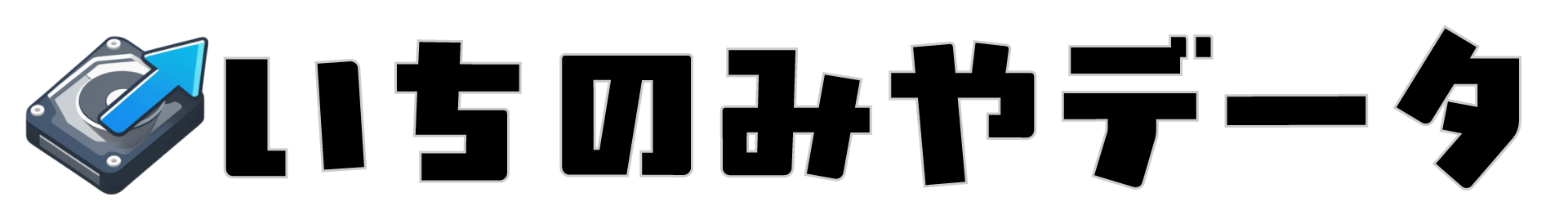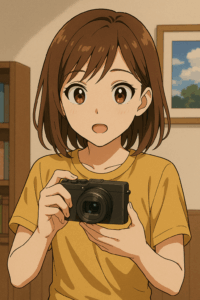【やさしく解説】政府機関のブルースカイ参入とその影響
Breaking News
何があった?(15秒で)
2025年10月17日、トランプ政権のホワイトハウスや国防総省など複数の米政府機関が一斉に分散型SNS「Bluesky」にアカウントを開設しました。しかし最初の投稿が「トランプ政権のハイライト集」という挑発的な内容だったため、リベラル層が多いとされるBlueskyユーザーから強い反発を受け、わずか48時間で約9万1千ものブロックを記録。外部トラッカーによれば、JD・バンス副大統領に次ぐ「2番目に多くブロックされたアカウント」となりました。
3つの要点
- ホワイトハウスなど政府機関が一斉参入
- 挑発的な初投稿にユーザーが猛反発
- 48時間で約9万ブロック達成し「2位」に
なぜ炎上?—事実関係を整理
参入のタイミングと背景:2025年10月17日、ホワイトハウス(@whitehouse-47.bsky.social)を筆頭に、国防総省、国土安全保障省、国務省、商務省など複数の政府機関が一斉にBlueskyへ参入しました。10月初旬から続く政府閉鎖と連邦職員削減という緊張した政治状況の中での参入でした。
挑発的な初投稿:最初の投稿は「やあ、Bluesky。われわれの『大ヒット作』をあなたが見逃していると思ったので、まとめてみました。一緒に素敵な時間を過ごすのが待ちきれません!❤️🇺🇸」という皮肉めいた文章と共に、トランプ大統領の"名場面"を集めた動画を掲載。AP通信は「リベラル層を刺激する明確な狙いがあった」と報じています。
記録的なブロック数:TechCrunchの報道によれば、48時間で約9万1千ブロックに到達し、フォロワーは約1万人という対比が際立ちました。外部トラッキングサイト「Clearsky」では、JD・バンス副大統領(夏から最多ブロック1位)に次ぐ2番目にブロックされたアカウントとして記録されています。
波及効果:その後も政府閉鎖を巡って民主党を非難する投稿や、トランプ政権への抗議デモを茶化すような内容を連投。これに対し、Blueskyユーザーは大量ブロックだけでなく、「ホワイトハウスアカウントと交流した全ユーザーをブロックするリスト」まで作成されるなど、徹底的な拒絶反応を示しました。
Blueskyは「ユーザー主権」のSNS
BlueskyはAT Protocol(Authenticated Transfer Protocol)上の分散型SNS。ユーザーが「何を見るか」を自分で決められる設計が最大の特徴です。モデレーション(表示方針)、アルゴリズム(カスタムフィード)、ブロックリストなどを自由に選択・カスタマイズでき、「見たくないものを見ない自由」を完全にコントロールできます。
Blueskyの3つの革新的機能:
- カスタムフィード:「猫の写真だけ」「科学ニュースのみ」など、ユーザーや第三者が作成した独自のアルゴリズムを選んでタイムラインを構築できます。公式の「Discover」以外にも無数のフィードが公開されており、複数同時に使えます。
- 選択可能なモデレーション:標準のモデレーション以外に、コミュニティが運営する「ラベラー」(モデレーションサービス)を追加可能。ハラスメントや不適切コンテンツへの対応レベルを自分で調整できます。
- 公開ブロック&共有ブロックリスト:ブロックは公開データとして扱われ、「政治色の強いアカウント全部ブロック」のようなリストを作成・共有できます。これにより一括ブロックが容易で、今回の政府アカウントへの対応も加速しました。
📌 AT Protocolとは?
Blueskyの基盤となる分散型プロトコル。中央管理者が存在せず、ユーザーが自分のデータを所有し、サーバー間を自由に移動できる設計です。MastodonのActivityPubと似ていますが、AT ProtocolはグローバルなSNS体験を重視し、アルゴリズムとモデレーションの選択肢を提供する点が異なります。ブロックチェーンは使用していません。
今回の騒動が示したこと
発信戦略とプラットフォーム設計のミスマッチ
従来のSNSなら「炎上=拡散=注目獲得」が成立しますが、Blueskyではブロックもカスタムフィードも容易なため、不快なコンテンツは即座に視界から消えます。挑発的な初投稿は大量ブロックを招いただけで、エンゲージメントは二桁台に留まりました。Gizmodoは「最強権力者のアカウントなのに、低エンゲージメントという皮肉な結果」と評しています。
ユーザー層と政治コンテンツの相性
AP通信は「Blueskyは左派寄りのユーザーに人気」と表現。実際、2024年の米大統領選後、XからBlueskyへ移住するリベラル層が急増し(2024年11月に200万人増)、現在のユーザー数は約2000万人に達しています。政治色の強いアカウントは歓迎されづらく、エコーチェンバー化の懸念も指摘されています。
📊 Blueskyの急成長データ
- 2024年11月(大統領選後):200万人以上のユーザー増加
- 2025年10月現在:約2000万ユーザー(2024年9月の900万から2倍以上)
- 米App Storeで一時1位を記録(ChatGPT、Threadsを超える)
- 著名人の移住例:マーク・ハミル、ジョージ・タケイ、AOC議員など
読者ができる「4つの自衛策」(3分で)
Blueskyの特徴を活かして、快適なSNS環境を自分で構築しましょう:
- 1. ブロック/ミュートの活用:見たくないアカウントは即ブロック(完全遮断)、一時的に距離を置くならミュート。ブロックは公開データですが、誰がブロックしたかは相手には通知されません。
- 2. カスタムフィードの選択:標準の「Following」「Discover」以外に、「OnlyPosts(リポストなし)」「猫画像専用」「科学ニュースのみ」など無数のフィードがあります。複数をピン留めして使い分けると、"見える世界"を柔軟に調整できます。
- 3. ラベラー(モデレーター)の追加:公式以外のモデレーションサービスを追加して、ハラスメントや政治的コンテンツなどへの対応を強化できます。コミュニティごとに独自のラベラーがあり、自分の価値観に合うものを選べます。
- 4. ブロックリストの活用:「政治bot全ブロック」「スパムアカウント一覧」など、有志が作成した共有ブロックリストを一括適用できます。一度に数百〜数千のアカウントをブロック可能。ただし、過度な使用はエコーチェンバー化のリスクもあります。
⚠️ プライバシーとセキュリティの注意
分散型SNSでも個人情報管理は自己責任です。二段階認証の設定、外部連携アプリの定期的な見直し、独自ドメインをハンドル名にする「Handle Update」機能(なりすまし防止)の活用をお勧めします。
専門家のひとこと
データ復旧技術者:分散型でもデータは公開されています。投稿・ブロック・いいね等は全てAT Protocol上で記録され、技術的には誰でも閲覧可能。二段階認証必須、パスワード管理アプリの使用、定期的なセキュリティ設定見直しが重要です。
プログラミング講師:Blueskyの「Composable Moderation(組み立て可能なモデレーション)」は教育的にも優れた設計です。ユーザーがアルゴリズムとモデレーションを選択できる透明性は、今後のSNSの標準になる可能性があります。AT Protocolのドキュメントは技術学習にも最適です。
Webエンジニア:「炎上耐性」はプラットフォームの機能設計に大きく依存します。Xでは炎上=拡散=リーチ拡大ですが、Blueskyでは即ブロック&フィード除外で終了。挑発的コミュニケーション戦略は分散型SNSでは逆効果です。政府や企業はプラットフォームの文化を理解した上で参入すべきでしょう。
まとめ
トランプ政権のBluesky参入騒動は、「見たくないものを見ない自由」を設計思想とするSNSでは、従来の注目獲得戦略が通用しないことを鮮明に示しました。挑発的な投稿は大量ブロックを招き、フォロワーよりブロック数が9倍多いという前代未聞の結果となりました。
Blueskyはユーザー主権を重視した革新的なプラットフォームですが、同時にエコーチェンバー化のリスクも抱えています。カスタムフィード、選択可能なモデレーション、共有ブロックリストといった機能は、快適なSNS体験を提供する一方で、異なる意見との接触を減らす可能性もあります。
今回の騒動は、政治コミュニケーションがどうあるべきか、SNSプラットフォームの設計がユーザー行動にどう影響するかという重要な問いを投げかけています。分散型SNSの時代において、発信者はプラットフォームの文化と機能を理解した上で戦略を立てる必要があるでしょう。数値は変動しますが、この構図は当面続きそうです。
🔗 参考情報
- 日本経済新聞「トランプ政権、SNS『Bluesky』にアカウント開設 挑発投稿連発」(2025年10月20日)
- Gizmodo「White House Invades Bluesky to Troll, Predictably Gets Mass Blocked」(2025年10月18日)
- TechCrunch、AP通信ほか各種報道
- Clearsky(Blueskyブロック数トラッキングサイト)
※本記事は2025年10月21日時点の公開情報に基づきます。ブロック数等の数値は外部トラッカーによる非公式推計であり、変動する可能性があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。