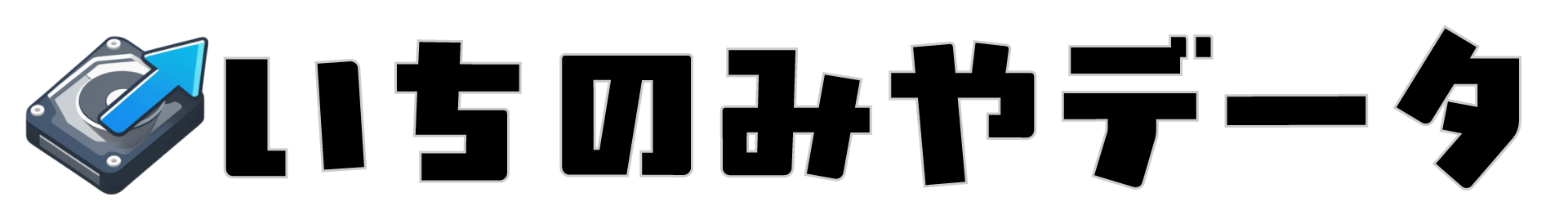5つの対策で安心!|巧妙化するSMS・架電フィッシング詐欺
【緊急警告】7月急増中!SMSと電話の「連携型フィッシング詐欺」からあなたの財産とデータを守る方法
最近、巧妙化するサイバー犯罪の手口が、私たちの身近な生活を脅かしています。特にデータセキュリティの専門機関であるトビラシステムズの調査で、2025年7月に「SMS(ショートメッセージ)と電話(架電)を組み合わせた新しいフィッシング詐欺」が急増していることが明らかになりました。
これは、宅配業者や金融機関を装ったSMSでまず注意を引き、その後に電話や自動音声を巧みに利用して個人情報や金銭を騙し取ろうとする、非常に悪質な手口です。まるで、巧みな釣り師がキラキラ光るルアー(偽SMS)で魚(私たち)を誘い、見えない釣り針(偽電話)で釣り上げようとするようなものです。
データ復旧エンジニアとして、私たちはこの種の詐欺が原因で大切なデータや財産を失い、途方に暮れるお客様を数多く見てきました。本記事では、この連携型フィッシング詐欺の具体的な手口と危険性、そしてあなたの財産とデータを守るために今日から、いえ、今すぐ実践すべき対策を、データ保護の専門家の視点から徹底解説します。
1. 7月急増!SMSと電話を組み合わせた「連携型フィッシング詐欺」の実態
トビラシステムズの調査によると、2025年7月に特に目立ったのは、従来のSMSフィッシング詐欺に「電話」を組み合わせることで、より巧妙化・自動化された手口です。
- 手口の巧妙化:まず、金融機関などをかたり、偽の窓口の電話番号が記載されたSMSが送られてきます。このSMSは、一見すると本物そっくりで、ターゲットの警戒心を巧みに解きます。
次に、記載された電話番号にかけ直すと、「重要なお知らせがあります。SMSで詳細をご希望の方は1を押してください」といった自動音声が流れ、被害者にダイヤル操作を促します。この自動音声とSMSの連携により、詐欺のプロセスが自動化され、より多くの被害者を効率的に狙えるようになっています。
ダイヤル操作を行うと、偽サイトのURLが記載されたSMSが改めて送られてきて、そこで個人情報や金融情報を入力させる仕組みです。
- 国際電話と詐欺SMSの傾向:迷惑電話番号の約6割が国際電話であり、特にアメリカ・カナダ(+1)、中国(+86)からの着信が多い傾向にあります。詐欺SMSでは「宅配事業者」(52.1%)をかたるものが最多で、特に「佐川急便」をかたる手口が急増しています。次いで「金融・決済サービス」(30.6%)をかたる手口も多く、「三菱UFJニコス」「Mastercard」「JCB」といったクレジットカードブランドが悪用されています。また、「国税庁」をかたるSMSも多発しており、税金に関する不安を煽る手口も確認されています。
この連携型詐欺は、私たちの「緊急性」や「不安」を巧みに利用し、冷静な判断力を奪うことを狙っています。普段から利用しているサービスを装うため、誰もが被害に遭う可能性があります。
2. 財産とデータを奪われる恐怖… あなたに起こりうる壊滅的被害
このような巧妙なフィッシング詐欺に一度引っかかってしまうと、その被害は金銭的なものに留まらず、個人情報や企業データといったかけがえのないデジタル資産にも及びます。
中小企業の場合:
- 取引先や金融機関を装った偽のSMSと電話に騙され、緊急の振込を指示される。結果、会社の運転資金が不正に送金され、事業継続が困難になる。
- 会社の重要な機密データ(顧客情報、製品開発データ、財務情報)を不正に抜き取られ、情報漏洩による信用失墜や損害賠償問題に直面する。
- オンラインバンキングの認証情報が盗まれ、気づかないうちに会社の口座が空になる。これは、まるで会社の金庫が丸ごと盗み出されるような、企業存続に関わる壊滅的な打撃となります。
個人の場合:
- 銀行やクレジットカード会社をかたる偽サイトに個人情報やパスワード、暗証番号を入力してしまい、クレジットカードの不正利用や口座からの不正送金が行われる。
- 大切なスマートフォンやパソコンに保存された写真、動画、連絡先などの個人情報が盗み出され、悪用される(例:なりすまし、脅迫)。
- パスワードを使い回していた他のオンラインサービスも乗っ取られ、SNSアカウントやオンラインゲームのデータが消失・悪用される。これは、大切な財布を盗まれるだけでなく、すべての個人情報が抜き取られてしまうような、耐えがたい不安と損失をもたらします。
3. 【プロが推奨】騙されないための「鉄壁のスマホ・PC防衛術」
巧妙化する詐欺からあなたの財産とデータを守るためには、日頃からの警戒と具体的な対策が不可欠です。
【最優先】怪しいSMSや電話への「絶対無視」と「確認」
- 不審なSMS・電話は「無視」が鉄則:身に覚えのないSMSのリンクは絶対にクリックせず、記載された電話番号にもかけ直さないでください。また、心当たりのない電話や国際電話には出ないようにしましょう。相手はあなたの動揺を誘い、冷静な判断力を奪おうとします。
- 正規の方法で「確認」を怠らない:もしSMSや電話の内容に不安を感じたら、そのサービスを提供している企業や金融機関の「公式の問い合わせ先」(公式サイトに記載されている電話番号など)に自分で連絡を取り、事実を確認しましょう。SMSや電話で指示された連絡先には絶対にかけてはいけません。
【日常の習慣】デジタル社会の自己防衛力を高める
- 個人情報のオンライン入力は慎重に:SMSやメールで送られてきたリンク先では、パスワードやクレジットカード番号などの個人情報を絶対に入力しないでください。重要な情報を入力する際は、必ず自分で公式サイトのアドレス(URL)を確認し、直接アクセスするようにしましょう。
- パスワードの強化と多要素認証の活用:複雑なパスワードを設定し、複数のサービスで使い回しはしないこと。可能であれば、指紋認証、顔認証、ワンタイムパスワードなどの「多要素認証」を有効にすることで、不正アクセスのリスクを大幅に低減できます。
- 常に最新のセキュリティソフトを導入:お使いのスマートフォンやPCに信頼できるセキュリティソフトを導入し、常に最新の状態に保ちましょう。これにより、ウイルスやマルウェアの感染を防ぐことができます。
- 家族や友人と情報を共有:詐欺の手口は常に進化しています。家族や友人、同僚と詐欺に関する最新情報を共有し、互いに注意喚起し合うことで、社会全体の防衛力を高めることができます。
【万が一の備え】データのバックアップと専門家の確保
- 定期的なデータバックアップ:どんなに注意していても、詐欺やサイバー攻撃の被害に遭う可能性はゼロではありません。大切なデータは、外付けHDDやクラウドサービスなど、常に複数の場所に定期的にバックアップしておきましょう。これが、失われたデータを復旧させるための最後の砦です。
- データ復旧業者の連絡先を控えておく:万が一、データが盗まれたり、消失したりした場合に備え、信頼できるデータ復旧業者の連絡先を控えておきましょう。迅速な対応が、データの復旧成功率を大きく左右します。
4. 被害に遭ってしまったら:冷静な初期対応が被害拡大を防ぐ
もし、あなたがフィッシング詐欺の被害に遭ってしまったと気づいたら、慌てずに冷静な初期対応を取ることが、被害の拡大を防ぐために最も重要です。
- すぐに利用停止・変更を行う:不正利用された可能性のある金融機関やクレジットカード会社、オンラインサービスに直ちに連絡し、口座の凍結やカードの利用停止、パスワードの変更などの措置を依頼してください。
- 警察に相談・被害届を提出する:最寄りの警察署またはサイバー犯罪相談窓口に連絡し、被害状況を詳細に説明して相談しましょう。被害届を提出することで、今後の捜査や解決に繋がる可能性があります。
- 通信事業者への相談:SMSや電話による被害の場合、利用している携帯電話会社にも相談し、迷惑メッセージブロックなどの対策を検討してもらいましょう。
- データ復旧の専門業者に相談:もしデータが消失したり、アクセスできなくなったりした場合は、自己判断で操作を続けず、データ復旧専門業者に相談してください。プロの知識と技術で、失われたデータの回復を試みることができます。
詐欺に遭ってしまったことは恥ずかしいことではありません。一人で抱え込まず、早めに専門機関に相談することが、被害を最小限に抑える最善策です。
まとめ:警戒心と準備が、あなたのデジタル資産を守る盾となる
SMSと電話を組み合わせたフィッシング詐欺は、私たちのデジタル社会における新たな脅威として急増しています。巧妙な手口は、誰もが被害に遭う可能性を秘めています。
しかし、過度に恐れる必要はありません。不審なSMSや電話には決して反応せず、公式な情報源での確認を怠らないこと。そして、パスワードの強化、多要素認証の利用、定期的なデータバックアップといった基本的なセキュリティ対策を徹底することが、あなたの財産とデータを守る「最強の盾」となります。
万が一被害に遭ってしまったとしても、慌てずに金融機関、警察、そしてデータ復旧の専門家といった「プロの力」を借りることで、被害を最小限に抑え、大切なデータを取り戻せる可能性があります。警戒心と準備を常に怠らず、安全で安心なデジタルライフを送りましょう。
参考ニュース
タイトル: 「SMSと架電を組み合わせた新たなフィッシング詐欺」の手口が発生中【トビラシステムズ調べ】(Web担当者Forum)
出典: Yahoo News IT
公開日: 2025-09-15
本記事の内容は公開時点の情報に基づいています。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。なお、記事の翻訳・編集には一部生成AIを活用しています。